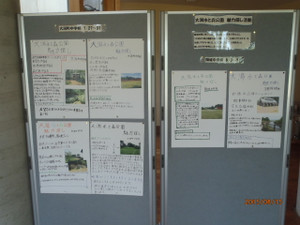ノルディックウォーキング教室開催しました!
平成27年8月29日、講師に室岡美穂子先生をお迎えし、
《ノルディックウォーキング教室》をおこないました p(^ω^q)![]()
室岡先生による初めてのノルディックウォーキングの教室です![]()
ノルディックウォーキングについて紹介いただき、
ポールを使ってストレッチ!
ポールをなんとなく持って歩いてみるところからスタート![]()
するとなんとなく地面に引っかかるポイントがあるはず・・・
そこにポールを付いて、ぐっと押し出してウォーキングするんです!
感覚をつかむのもなかなか難しい~(m´・ω・`)m
雨が少し当たっていましたが、外で歩いてみましたよ![]()
小回りのコースですが、実際にポールを使うことで
「普通に歩くより楽」、「いつもより早く歩ける」という声が
聴こえてきましたヾ(o・ω・o)ゞ![]()
ご参加いただいた皆さん、室岡先生、
どうもありがとうございました(b´∀`d)
次回は平成27年9月19日の開催です!
ご参加希望の方はお早めにお申し込みください![]()
お待ちしております((((o・ω・)o)))![]()